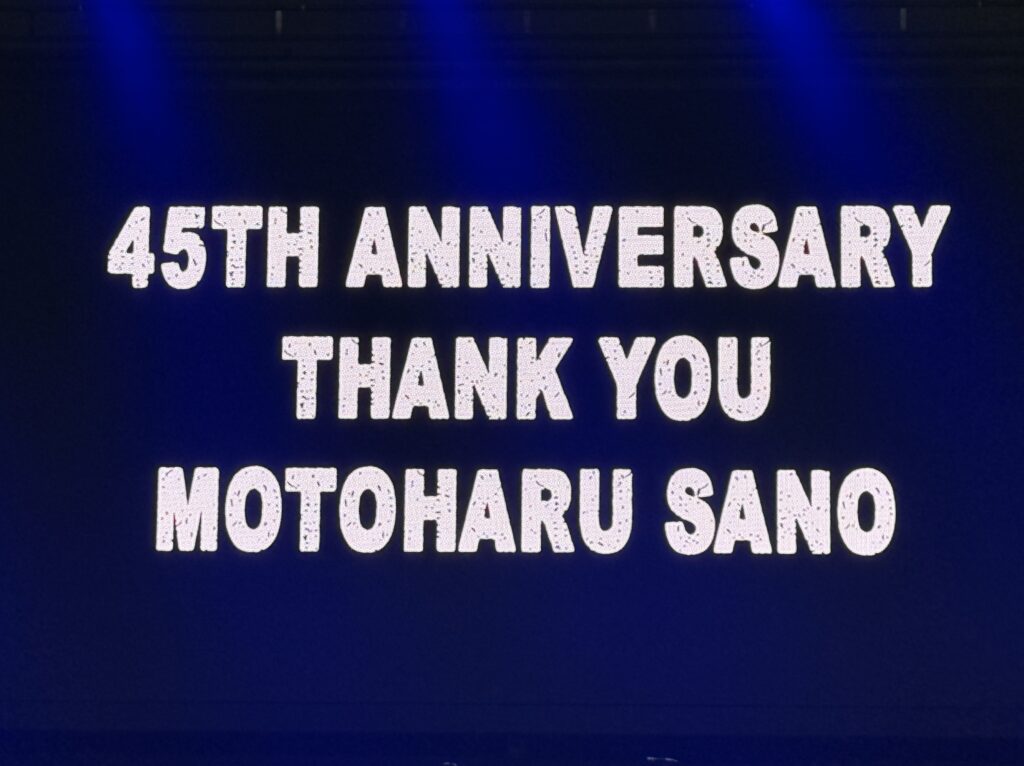12月7日(日)「横浜BUNTAI」で佐野元春のデビュー45周年とThe Coyote Bandの結成20周年を記念するツアー・ファイナルを観た。ライブ冒頭の「ここで演奏するのは40年振り」というMCで気づいたが、ここは旧「横浜文化体育館」の跡地だったのか(2024年4月に立て替えオープン、横浜文化体育館の略称「横浜文体」にちなんで「横浜BUNTAI」とした模様。わかりにくい)。


5千人収容の会場は横長のレイアウトで、大きなライブハウスといった趣き。佐野デビューの地、横浜でのツアー・ファイナルであること、「YOKOHAMA UNITE音楽祭」の一環であることから、このライブが「特別なもの」になることが事前にアナウンスされていた。



佐野元春について
僕にとって、1980~90年代の佐野元春は優れたシンガーソングライターであると同時にサブカルチャーやポップカルチャーの先生だった。山下達郎と同様にラジオDJとしてオールディーズを系統立てて教えてくれただけでなく、ジャズやR&B、ファンク、パブロック、ニューウェーブ、オルタナティブロックなど多岐にわたる音楽を紹介してくれた。ボブ・ディラン経由でアレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアック、ウィリアム・バロウズといったビート・ジェネレーションの著書や、マルクス・ブラザースの古いスラップスティック映画を紹介してくれたのも彼だ。
佐野の45年のキャリアを通じて最も好きなアルバムは「Visitors(1984年)」。デビューアルバム「バック・トゥ・ザ・ストリート(1980年)」から渡米直前にリリースされたベスト盤「No Damage(1983年)」までのアルバムとはサウンド、リリック、メロディのすべてが変異してしまったことからリリース当初は拒絶していたが(僕も若かった)、時が経つにつれて「Visitors」の革新性に惹かれていった。ビートルズの「Rubber Soul」から「Revolver」への大きなジャンプのように、今思えば、佐野の「No Damage」から「Visitors」への変化も「ホップ、ステップ」の過程をすっ飛ばした「ムーンショット」と云える革新だった。1983年のニューヨークのパワフルなビートと、歌詞、メロディが完全に一体化した「Visitors」は、今聴いても抗えない魅力を放っている。

一部(Hayabusa Set)、一つ目の「特別」
ライブは二部構成になっており、一部は1980~90年代の自作曲をカバー(再定義)した最新作「Hayabusa Jet」収録曲。2人の女性コーラスが演奏に加わったことが、最初の「特別」だ。やはり、初期のポップな楽曲には華やかなコーラスが似合う。
シングル曲「Youngbloods(1985年)」「つまらない⼤⼈にはなりたくない(原題『ガラスのジェネレーション』1980年)」「だいじょうぶ、と彼女は言った(1999年)」「街の少年(原題『ダウンタウン・ボーイ』1981年)「誰かが君のドアを叩いている(1992年)」に加え、「欲望(1993年)」「レイン・ガール(1993年)」といった非シングル曲が瑞々しく光る。
特に、アンビエントに再構築された「欲望」は、追い立てられるようなビートと佐野のボーカル、ゴスペル調の「Rescue me, rescue me」の女性コーラスが相まって、前半のハイライトの一つとなった。
「昔よく口ずさんだメロディー」の連打に、隣の女性客が大声で合唱していたが(オアシスのライブを観てから気にならなくなった)、僕も思わずサビを歌ってしまった。
二部(Coyote Set)、二つ目の「特別」
二部はThe Coyote Band結成以降の楽曲中心。2005年に一回り若いバンドメンバーを得た佐野の音楽は、ギターサウンドをフィーチャーした、よりオルタナティブな感触のものに変容していった。従来の、メロディに合うように語感を重視して選択されたナンセンスな歌詞や英語詞は陰を潜め、より直接的なメッセージが日本語で歌われるようになった。メロディと言葉(歌詞)のバランスで云えば、言葉の比重が大きくなった印象だ。覚えやすくて歌いたくなるようなメロディが減っていくのに伴い、佐野の新しい音楽を以前のように熱心に聴かなくなった(それでもCoyote Bandの演奏は素晴らしかったので、アルバムが出れば聴き、ライブは観続けた)。
5曲目の「愛が分母(2019年)」からコーラスがステージに戻り、「純恋(2017年)」「La Vita è Bella(2012年)」とポップな佳曲が続く。
「新しい世界(原題『ニュー・エイジ』1984年)」では、朽ちた戦車が横たわる荒廃した街のビジュアルイメージ(核戦争後の世界だろうか?)がステージ背景のLEDビジョンに映し出された。佐野がニューヨークの地下鉄からコニーアイランドのボードウォーク(遊歩道)を見てインスピレーションを得たと言われる、同曲の歌詞を引用してみよう。
誰も愛しあっていない
誰も信じあっていない
君と今夜は闇をくぐって
小舟を漕ぎ出したい
That’s the meaning of life(それが人生の意味)
「新しい世界(原題『ニュー・エイジ』)」
スクリーン上の過酷な映像を観ながらこの曲を聴くと、単身渡米して「Visitors」制作中の佐野が絶望の淵に踏みとどまりながら見た、一瞬の希望を歌ったものであることが分かる。
一方で、斯様にメッセージ性の強い映像はオーディエンスのイメージを限定してしまうので、僕はこの手の映像演出は好まない。さらに言えば、近年の佐野のステージでは歌詞の一部をスクリーンに映写するが、観客はその切り出された言葉に特別な意味があり、特に伝えたいメッセージであるかのように受け取ってしまうので(少なくとも僕はそうだ)、そういった演出がアーティストの意向だとしても、僕はもっと純粋に音楽を受け取りたい。
「スウィート16(1992年)」「サムデイ(1981年)」の後に近年作「明日の誓い(2022年)」を挟み、このツアーで初めて「クリスマス・タイム・イン・ブルー」が演奏された。これが2つ目の「特別」で、女性コーラスが活きる。「約束の橋(1989年)」で本編終了。
アンコール、三つ、四つ目の「特別」
アンコールでは「Sugartime(1982年)」(三つ目の「特別」)、「スターダスト・キッズ(1982年)」「ソー・ヤング(1983年)」「アンジェリーナ(1980年)」と初期楽曲の熱演が続く。佐野がこれほど声を張り上げて観客を煽る姿は久しぶりに観た。従来は「悲しきRadio」のアウトロにあったコール&レスポンスは「アンジェリーナ」とのメドレーで演奏され(四つ目の「特別」)、5千人の観客の熱狂と共にライブは大団円を迎えた。
時を超え、2025年の今にフックする楽曲たち ~ そしてビートは続く
アンコールで演奏された「Sugartime」と「スターダスト・キッズ」は佐野の初期楽曲の多層的な構造がよく分かる好例だ。両曲とも主題はラブソングで、ポップなサウンドとメロディでシュガーコーティングしているものの、その中身にはハードなパンチラインが含まれている。
曲名からして溶けてしまいそうな甘いラブソング「Sugartime」では、唐突に「Everybody ひとりだけじゃ Everybody 闘えない」という反骨的な歌詞が挿入されるが、華やかなサウンドメイキングによって違和感なく聴ける。
ナンセンスな(しかし聞き手のイメージを喚起する)歌詞の「スターダスト・キッズ」は「本当の真実がつかめるまで Carry on」と締めくくられる。元来「本当のこと」を意味する「真実」という言葉にわざわざ「本当の」を付け加えた歌詞は、SNS上の玉石混交な情報やフェイクニュースの海で溺れてしまいそうな現代を生きる我々に向けて「すべてを疑え」と警鐘的に響く。
「木を隠すなら森の中」のことわざ通り、佐野は楽曲全体に聞き心地のいい装飾を施すことによって、主題(ラブソング)と異物(メッセージ)の同質化に成功している。この程よい異物感は他のソングライターの楽曲では感じられないもので、佐野のポップスを特別なものにした要素の一つである。メッセージだらけの曲を聴いても疲れてしまうだけだろう。
興味深いのが、本編2曲目に演奏された「つまらない⼤⼈にはなりたくない(原題『ガラスのジェネレーション』」だ。今回の再定義によって、終盤の「つまらない⼤⼈にはなりたくない」というキラーフレーズが曲名に昇格してしまった。これはCoyote Band結成以降、言語表現がより直接的になっていった佐野の創作上の気分の変化によるものだろう。
「クリスマス・タイム・イン・ブルー」は、ジョン・レノンの「Happy Christmas」の手法を使った「愛してる人も 愛されてる人も 泣いてる人も 笑っている君も 平和な街も 闘ってる街も メリー・メリー・クリスマス Tonight’s gonna be alright」という対になった歌詞の後に、マザーグースの童謡の一節” Ring-a-Ring-o’ Roses “を借用して「世界中の子供たち (せめてクリスマス・イブの今夜だけでも)バラの輪っかをつくろう」と歌いかける、ミッション系学校出身の佐野ならではの視点を持つ曲だ。この曲が発表されてから40年が経過したが、1990年代に冷戦が終結しても戦火が止むことはなく、むしろ2000年代以降は各地の紛争が多極化し、世界の分断が加速してしまった。久々にライブで聴き、混迷を極めて出口の見えない今日においても、この曲は「平和を願う祈り」として機能していると感じた。
今夜は多くの初期楽曲に触れて、その普遍性を再認識することができた。Coyote時代の曲にも心の奥まで届くものがあり、45年という長いキャリアを祝うに相応しい、素晴らしいショウだった。